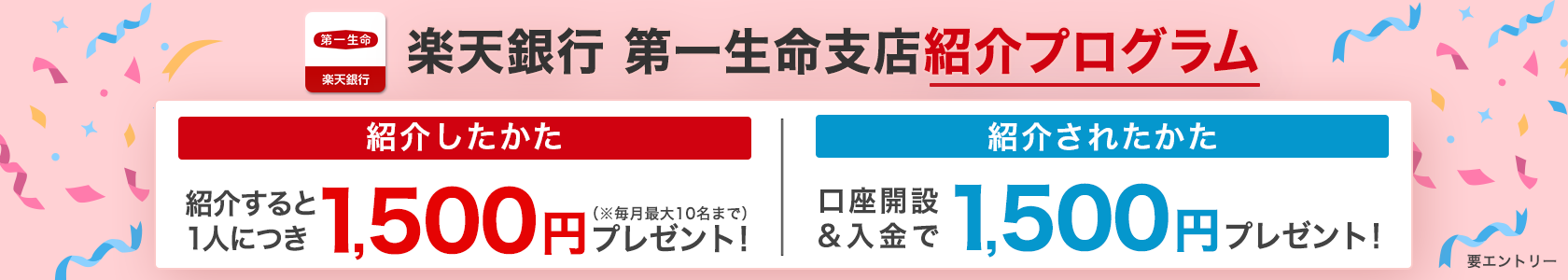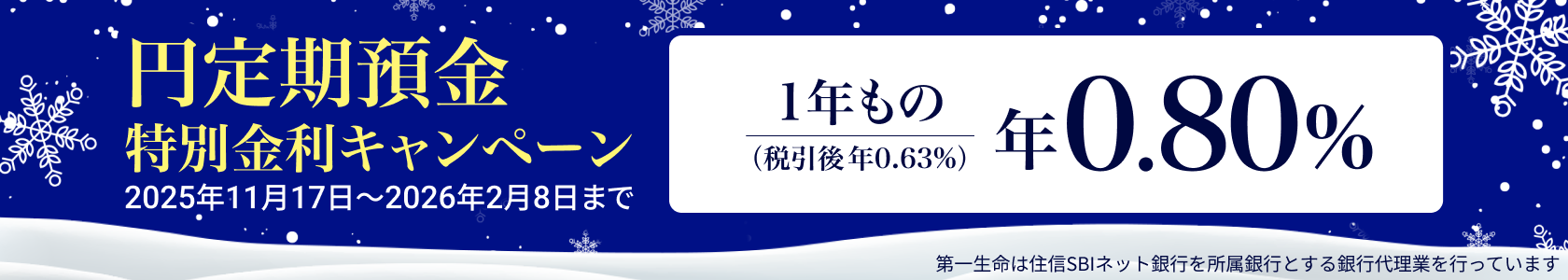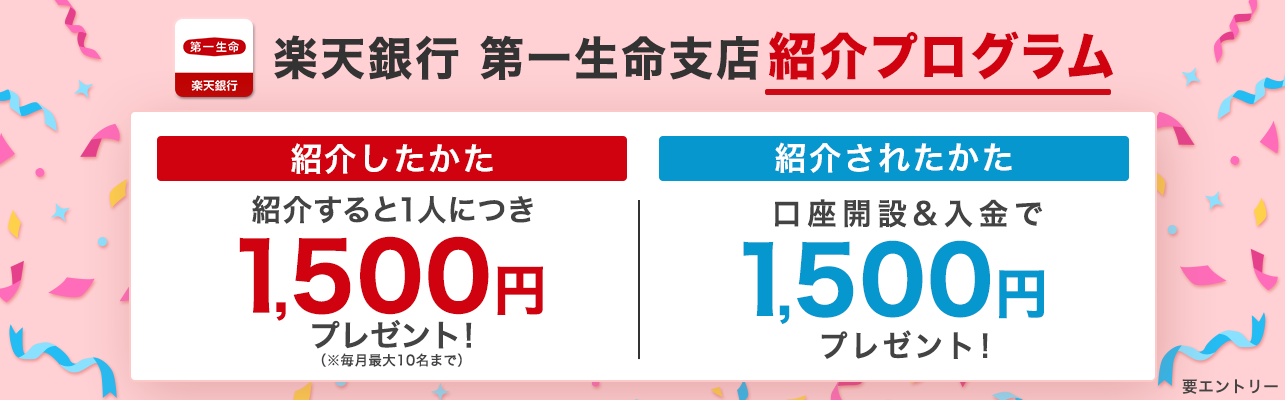掲載日:2025/10/20
目次
1.奨学金とは?簡単にわかりやすく解説
2.奨学金制度の全体像と種類
3.奨学金の金額・支給方法・支援内容
4.奨学金返済(返還)の仕組みと注意点
5.奨学金のメリット・デメリットと将来への影響
6.まとめ−自分に合った奨学金制度のチェック方法と最初の一歩
奨学金とは?簡単にわかりやすく解説
奨学金の基本概念と特徴
奨学金とは、経済的な理由で進学が難しい学生に対して、学費や生活費の一部を支援する制度です。日本では主に、文部科学省所管の独立行政法人である「日本学生支援機構(JASSO)」が運営する奨学金が広く知られています。そのほか、地方自治体・企業・大学独自の制度などさまざまな団体が独自に奨学金制度を設けており、学びたいという意欲を持つすべての学生が進学のチャンスを得られるよう、国と社会が支援しています。
奨学金には「返済の必要がない給付型」と、「将来的に返済が必要な貸与型」があり、それぞれに条件や仕組みが異なります。
特に大学や専門学校など高等教育機関では費用が大きくなるため、多くの学生が奨学金を活用して学びを続けています。
奨学金制度の全体像と種類
給付型奨学金と貸与型奨学金の違い
奨学金には大きく分けて「給付型」と「貸与型」の2種類があります。
給付型奨学金は返済の必要がない支援で、経済的に困難な家庭や学業成績が優秀な学生を対象に支給されます。特に「高等教育の修学支援新制度(文部科学省・JASSO実施)」では、住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯の学生を対象として、授業料・入学金の減免と給付型奨学金がセットで支給されています。
一方、貸与型奨学金は卒業後に返済が必要な制度で、無利子の「第一種奨学金」と、有利子の「第二種奨学金」に分かれています。第一種は学業成績や家計基準を満たす学生が対象で、第二種はより幅広い学生が利用可能です。借入額や返還方法を選択できる柔軟性があり、進学を支える重要な資金源として多くの学生が利用しています。
日本学生支援機構(JASSO)による奨学金制度の概要
日本学生支援機構(JASSO)は、文部科学省所管の独立行政法人で、日本最大の奨学金提供機関です。JASSOの奨学金制度は、全国の大学・短期大学・専門学校などに進学する学生を対象に、給付型と貸与型の両方を提供しています。
給付型奨学金は、家庭の収入状況や学業成績などに基づいて支給され、返済の必要がありません。貸与型奨学金は、第一種(無利子)と第二種(有利子)に分かれ、卒業後に分割で返済していく仕組みです。申請には、在学する学校を通じて行う「予約採用」と、入学後に申し込む「在学採用」のほか、被災・家計急変時の申し込み(家計急変採用、緊急・応急採用)があります。

民間・地方自治体・企業など他団体の奨学金支援制度
JASSO以外にも、さまざまな団体が奨学金制度を提供しています。地方自治体の制度では、地元出身者や地域定着を目的としたものが多く、企業の奨学金は特定の業種や専門分野の人材育成を目的に設けられています。
これらの奨学金の中には、返済不要の給付型や、一定期間の勤務を条件に返済が免除される制度もあります。地域や業種ごとに特徴が異なるため、自分の進路や将来の働き方に合った制度を探すことが重要です。
奨学金の金額・支給方法・支援内容
毎月・年間で受け取れる金額の目安
奨学金の支給額は、制度の種類や家庭の収入状況、進学先の形態(国公立・私立、自宅通学・自宅外通学)などによって異なります。
JASSOの給付型奨学金では、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯を対象に、月額4,400円から75,800円の範囲で支給されます。支援額は通学形態や学校種別によって変わり、授業料・入学金の減免とあわせて行われます。
(出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」、日本学生支援機構(JASSO)「給付奨学金の支給額」)
一方、貸与型奨学金には無利子の「第一種」と有利子の「第二種」があり、第一種では大学生の場合、月額20,000円から64,000円の範囲で設定されています。第二種ではより幅広く、月額20,000円から120,000円の範囲から1万円単位で選択可能です(出典:JASSO「第一種奨学金の貸与月額」/JASSO「第二種奨学金の貸与月額」)。
通常、奨学金は毎月指定の口座に振り込まれ、学費や生活費などに充てることができます。
学費・授業料・生活費など使い道のポイント
奨学金は原則として使途に制限がなく、授業料、教科書代、交通費、家賃、食費などに利用できます。ただし、貸与型奨学金は将来返済が必要な資金であるため、必要な額を見極め、計画的に利用することが大切です。無計画に借りると、卒業後の返済負担が大きくなるおそれがあります。
新制度や病院・看護師向け特別支援の紹介
看護師・保育士など、特定の職種を目指す学生を対象にした「修学資金貸付制度」もあります。これらは卒業後に一定期間、医療機関や福祉施設で勤務することを条件に返済が免除される場合があります。
また、2020年度から始まった「高等教育の修学支援新制度」では、経済的に厳しい家庭の学生に対して、授業料・入学金の減免と給付型奨学金が一体で支給される仕組みが整備されています。
奨学金返済(返還)の仕組みと注意点
貸与型奨学金の返還方法と猶予・免除制度
貸与型奨学金を利用した場合、卒業後から返済(返還)が始まります。返済方法には、毎月一定額を返す「定額返還方式」と、収入に応じて返済額が変動する「所得連動返還型」の2種類があります。後者は、経済的状況に応じた柔軟な返済が可能な仕組みとして注目されています。
返済が困難になった場合には、「返還期限猶予制度」や「減額返還制度」などの救済措置を申請することもできます。これにより、失業や病気、災害などにより返済が難しい場合でも、一定期間返済を猶予したり、返済額を減らしたりすることが可能です。
卒業後や就職後の返済計画・シミュレーション
奨学金の返済は、社会人生活において大きな負担となることもあります。たとえば、月に1万円〜2万円の返済が10年〜20年続くケースもあります。返済が始まる前に、将来の収入や生活費を見積もり、無理のない返済計画を立てることが重要です。
JASSOの公式サイトでは、返還額のシミュレーションができるツールも提供されています。進学前に一度試してみると、将来の見通しが立てやすくなります。(出典:JASSO「奨学金貸与・返還シミュレーション」)
困った時の相談窓口・支援団体情報
返済に困った場合や、制度について不明点がある場合は、まず在学中の学校の奨学金担当窓口に相談しましょう。また、JASSOには「奨学金相談センター」があり、相談が可能です。
奨学金のメリット・デメリットと将来への影響
奨学金を活用するメリット
奨学金の最大のメリットは、経済的な理由で進学をあきらめることなく、学びの機会を得られる点です。特に給付型奨学金は返済の必要がないため、将来の負担を軽減しながら学業に専念できます。
また、奨学金を受けることで、学費や生活費の心配が減り、アルバイトに追われることなく勉強や課外活動に集中できるという利点もあります。
デメリットや注意すべき落とし穴
一方で、貸与型奨学金には返済義務があるため、将来的に大きな負担になる可能性があります。特に、就職後の収入が想定より少なかった場合や、病気・失業などで収入が途絶えた場合には、返済が困難になることもあります。
また、奨学金を借りすぎてしまうと、社会人になってからの生活に大きな影響を及ぼすこともあるため、必要な金額を見極めて借りることが大切です。
進学・就職への影響
奨学金を利用することで、希望する進学先を選びやすくなり、将来のキャリアの選択肢が広がるというメリットがあります。一方で、返済の負担を考慮して、就職先や進学先を制限せざるを得ないケースもあります。
まとめ−自分に合った奨学金制度のチェック方法と最初の一歩
奨学金は進学を支える大切な制度ですが、その仕組みや条件を正しく理解して活用することが重要です。給付型か貸与型か、貸与額をいくらにするかなど、自分の状況に合った制度を選ぶことが、将来の安心につながります。
まずは、在学中・進学予定の学校の奨学金窓口に相談してみましょう。また、JASSOの公式サイトでは、奨学金の種類や申請方法、返還シミュレーションなど、役立つ情報が豊富に掲載されています。
進学は人生の大きな選択の一つです。奨学金という制度を正しく理解し、上手に活用することで、夢に向かって一歩踏み出す力につなげることができます。
関連リンク
→「大学の学費はいくらが平均?生活費などの費用も含めて解説!」
関連コラム
もっと見る